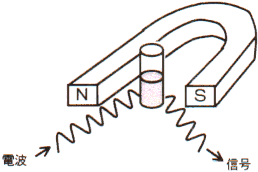| MRI(magnetic resonance imaging)は、磁石と電波で人体のいろいろな方向からの断面を正確に画像化する検査法で、1980年代初めに本格的な臨床応用が始まりました。 MRIは、高磁場で電波を使うことによって人体から発生する弱い電波を受信し、コンピューターで電波の発信場所・量を把握することにより画像を作り出します。 その画像分析から、正常部とは異なった病変部を診断します。 今日では、コントラスト分解能が向上し、また、被験者の体位を変えることもなく自由な断層の最像に優れているMRIは、脳・脊髄領域から、躯幹部・四肢領域へと広く臨床応用されるようになりました。 原理(NMR)と(MRI) NMR(nuclear magnetic resonance)は、核磁気共鳴のことで、「磁場(磁界)に置かれた原子核が特定の周波数(振動数)の電波に共鳴して、自ら電波を発信する現象」です。 この特定の周波数は磁場の強さと原子核の種類によって決まっています。
MRIは、磁気共鳴診断法とも呼ばれる「NMRを利用した画像診断法」です。 MRは、均一な対象(試料)からの信号を分析しますが、MRIは、構成要素の複雑な人間を対象とし、その信号を画像とするため、信号の発生位置(肝臓のどこからかなど)が細かく特定されます。 MRIは、「傾斜磁場*1によりNMRに位置情報を加えて信号の強度分布を示した地図」になります。 *1〔傾斜磁場]磁場強度にわずかな傾斜をつけ、信号の周波数や位相を異ならせる 磁場と安全性 MRIは、強い磁場と電波を使いますが、Ⅹ線最影に伴う"被曝"のようなことはなく無害です。 この電波はラジオ波(RF)に属し、FMラジオ放送やテレビ放送と周波数帯は同じ種類です。 検査に対して、心配することはありませんが、磁場を使うために検査を受けられない患者など、注意を要することもあります。(心臓ペースメーカーなどは禁忌) また、撮像時にトントンという大きな音がしますが心配ありません。この音は、傾斜磁場コイルに高速にカがかかったり切れたりして振動が起る際に生じる音です。耳栓を使用している施設も多いようです。 今日、MRIの可能性ははかりきれず、さまぎまな技術が考案されてきており、撮像時間の短縮化、非常に精細な血管像(MRA)などと、診断範囲がさらに広がってきています。 |